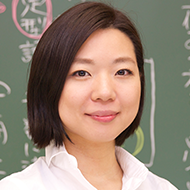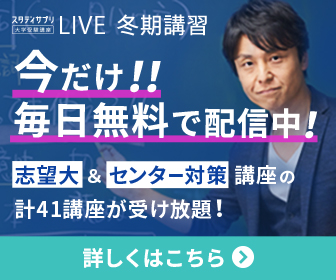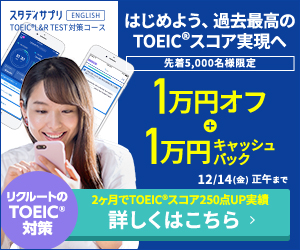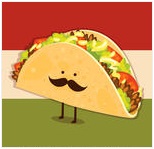スタディサプリ小学生向け国語の評判・口コミ
スタディサプリの国語は丁寧な読解力をつけるために、学年ごとにステップアップしていきます。
小学4年生では物語文の読解を中心に扱い、登場人物の心情を理解する解法を学びます。5年生では難易度があがる説明的文章の読解に入り、短い文章から長い文章まで読み解くトレーニングを進めます。6年生ではこれまで学習してきたことを組み立てて、複雑な設問に対応できるようなトレーニングを進めます。
各単元で用意されているドリルを使って理解度の確認をすることができます。復習としてドリルを進めて、点数がよくない単元を動画の授業で復習するということもできます。
授業の内容や進め方についてまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。
山崎 萌(やまざき もえ)先生 |
裏垣 暁広(うらがき あきひろ)先生 |
|---|---|
|
|
|
山崎先生は小学校4年生から5年生の基礎レベルを担当。 |
裏垣先生は小学校4年生から5年生の応用レベルを担当。 |
福嶋 淳(ふくしま じゅん)先生 |
|
|
|
|
福嶋先生は小学校6年生の基礎・応用レベルを担当。 |
|
小学校4年生から6年生まで順番にまとめています。見たい学年を選択すると、本ページの該当部分へスキップできます。
小学校4年生の国語
授業一覧
基礎レベル |
|
|
1.漢字① |
13.ごんぎつね② |
応用レベル |
|
|
1.言葉① |
13.説明文②-1 |
小学校4年生の国語の授業の評判
今回は小学校4年生で大事な基礎レベル「物語①」を受けてみました。担当は山崎先生です。
第一印象として、小学校の先生ぽい。はきはきとした関西弁で、軽快な説明をしていきます。まず「物語」を読む上で大事なポイントを説明してくれました。この説明は10分もかからず非常にコンパクトにまとまっています。その後に実際に問題に入っていきます。
物語の内容は以下の3つに分かれている。
- 場面…いつ、どこで
- 人物…だれが
- 事件…何をどうした、どうなった
いつどこでだれがどんな事件に遭遇したか。そしてどんな心情になったかがよく聞かれる。
うおおお。さっそく物語を読み解くコツがわかりました!夏休みの日記などを書くときも大事ですね。「いつ」「どこで」「だれが」「何をした」です!そして、この情報をもとに、登場人物の心情をつかむのです。
例)事件:先生に怒られた
まず、「先生に怒られた」という事件があったとしましょう。このときの「心情」悲しい?腹が立つ?色々考えられるでしょう。
でも、大事なのは、受け取り手(性格)によって、同じ事件でも感じ方は違うということです。
自分がどう感じるかではなく、本文に書いてることを読み解くのです。でも、「悲しい」とか感情をそのまま書いてないことがある。そういう時は言動に注意するべし。
例)泣いてしまった→悲しい
例)壁を殴った→腹が立つ
そうです。「読み解く」というのは、本文に書かれている情報をもとに、色々推理していくことでもあるんですね。そう考えると、国語って楽しいですね。
「読み解く」方法=解法がわかれば、問題を解くのも気が楽です。そう、推理とも言えるし、パズルみたいなものです。ぜひ山崎先生の授業を試しに受けてみてください。
小学校5年生の国語
授業一覧
基礎レベル |
|
|
1.漢字① |
13.注文の多い料理店(物語文)② |
応用レベル |
|
|
1.言葉① |
13.随筆文② |
小学校5年生の国語の授業の評判
今回私が受けたのは、小学校5年生で大事な「説明文①」です。担当は基礎レベルの山崎先生です。
関西の人は当たり前ですけど、関西弁の授業がすごい新鮮です。私は横浜出身ですからほぼ標準語で授業を受けてきました。でも山崎先生の関西弁の授業は不思議な魅力があります。
問いかけも「なんでやろ~?」って聞きますから、こっちも思わず
「なんでやろな?」って考えてしまいます。
テンポが良いのでしょうね。自然と先生の説明が耳に入ってきます。さてそれでは、実際に説明文をどのように読み解くのかを、以下のように説明してくれました。
説明文とは、あることがらについて詳しく説明した文章。
説明文は以下の3つで構成されている。
- 序論:話題(テーマ)を提示する
- 本論:詳しい説明=具体例
- 結論:話題に対するまとめ
ふむ。大人ならわかりますよね。でも小学校4年生ですから、一つ一つどういうものかを例え話を使って説明してくれました。
そしてその後、テキストに書いてある例文をチェックをさせながら一緒に読んでいきます(まだ練習問題に入っていません)。ここでチェックするのは、先に挙げた3つ、「序論」「本論」「結論」です。まずは説明文の構成をしっかりと理解させるために、丁寧にチェックさせながら解説しました。
これで約8分ほど。この次のパートで練習問題に入ります。いきなり問題を解かせるのではなく、解き方を理解してから問題に入るので安心です。
よく「国語はセンスだ」と言う人もいますが、それは間違いです。国語には解法があります。それはトレーニングを積み重ねて、実際に身につけることができます。山崎先生の授業、ぜひ受けてみてください。
小学校6年生の国語
授業一覧
基礎レベル |
|
|
1.漢字① |
13.論説文② |
応用レベル |
|
|
1.言葉① |
13.随筆文②-2 |
小学校6年生の国語の授業の評判
私が受けたのは基礎レベルの「随筆文①」です。担当は福嶋先生です。
随筆って何?本が好きな人は当たり前かもしれませんが、そうでない人は意外と知りません。私は教員をしており参考書などは読みますが、随筆は全く読みません。
随筆とは「エッセイ」ともいい、筆者の体験や記憶から得た知識をもとに、それに対する筆者自身お思いをつづった文章。
なるほど。そうですか。小学校でよく書く作文なんかは随筆になるんでしょうか?どうでしょう。それはともかく、随筆の読解方法の説明に入ります。
- 現在
- 過去の体験・記憶(回想)
- 現在→感想(教訓)を得る
ふむ。大事なのは「感想(教訓)」でしょうね。感想文でも、「楽しかった」ではなく、「これからは○○に気をつけよう」のほうが好評かなのは間違いない。そして、この構成をもとに読解方法に入ります。
1.筆者の着眼点を探す
→何に興味があるか
2.筆者の考えを読み取る
→目をつけたことに対してどう思っているか
3.テーマをつかむ
筆者が何を伝えたかったのか
ちょうど随筆文の構成に沿って、順番に読み取っていく感じですね。わかりやすい!
小4で物語文、小5で説明的文章を習いました。小6では随筆文が出てきます。それぞれどのような文章構成になっているかを理解して、それにあった読解方法を身につけていくことが大事なのですね。
福嶋先生の授業を通して、文章をただ読むのではなく、文章の構成を意識しながら読むことで、筆者が何を伝えたいかを正確に読み解くことができそうです。ここまでの説明時間は約8分ほど。この後実際に練習問題に入っていきます。
以上、スタディサプリの「小学生の国語の授業一覧と評判」でした。